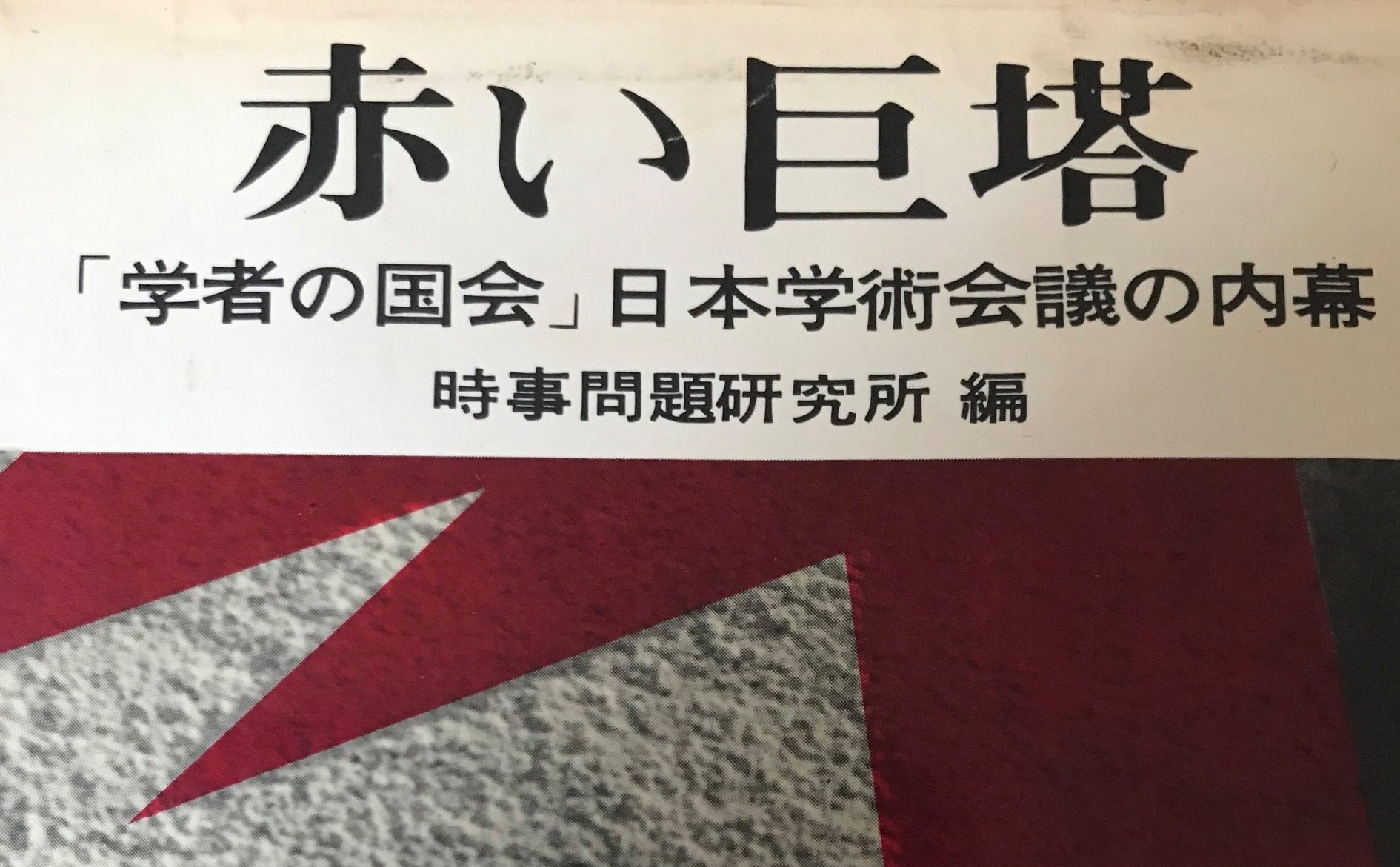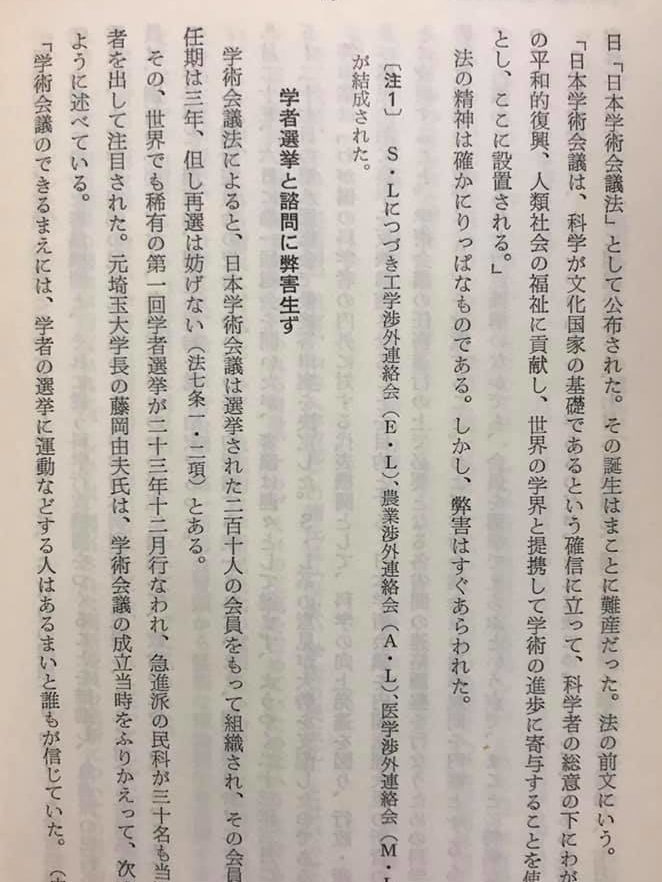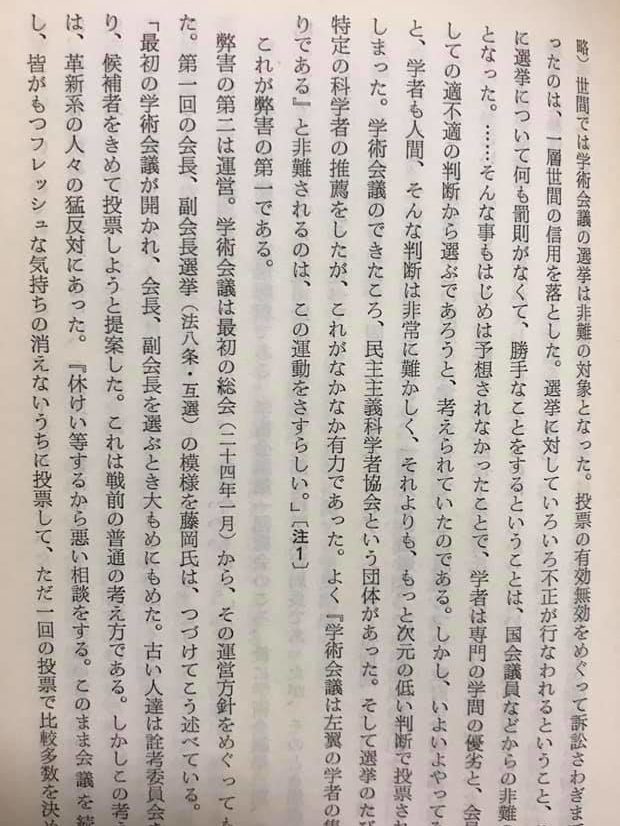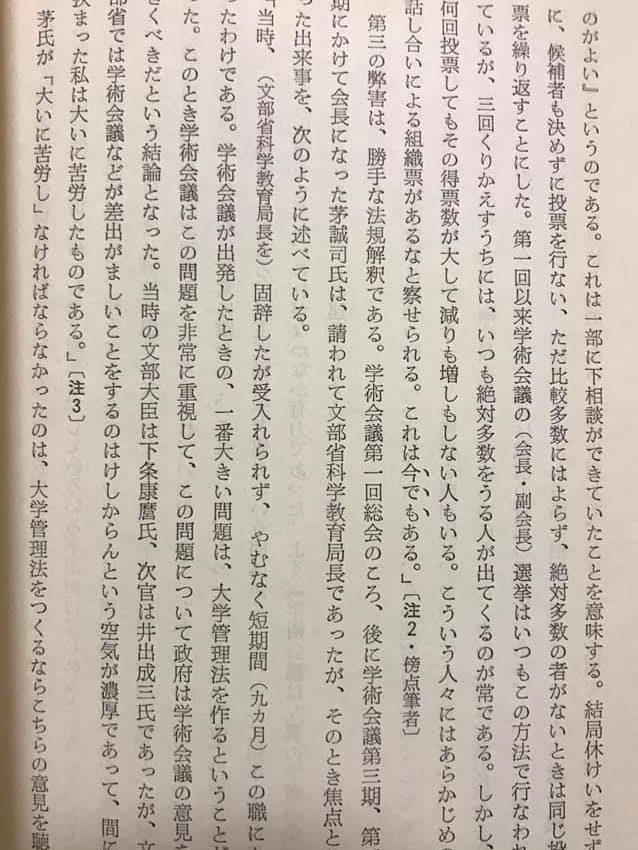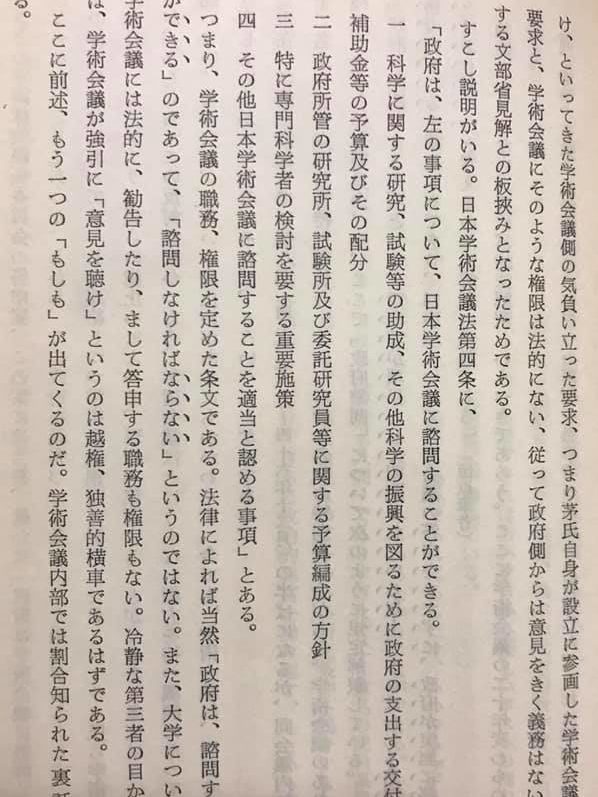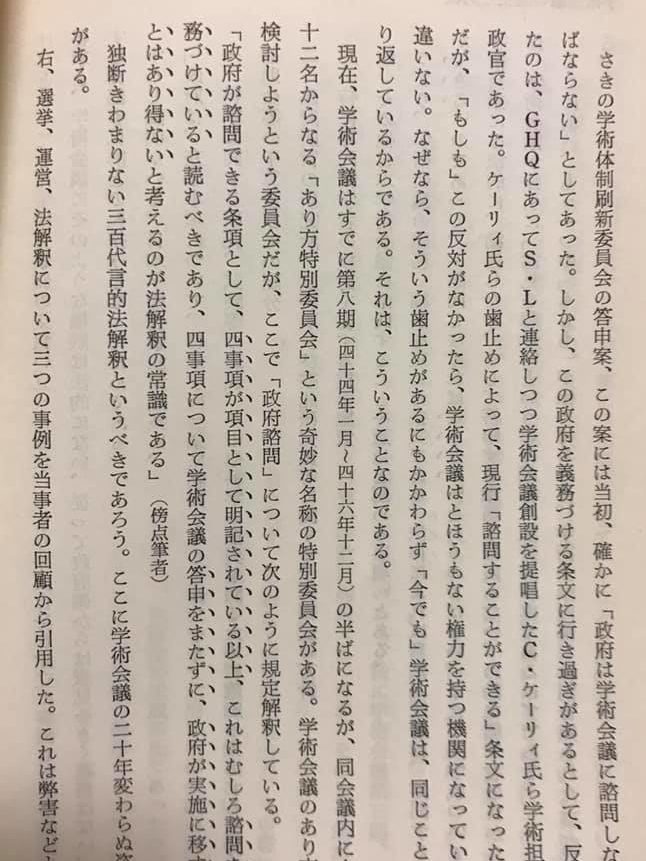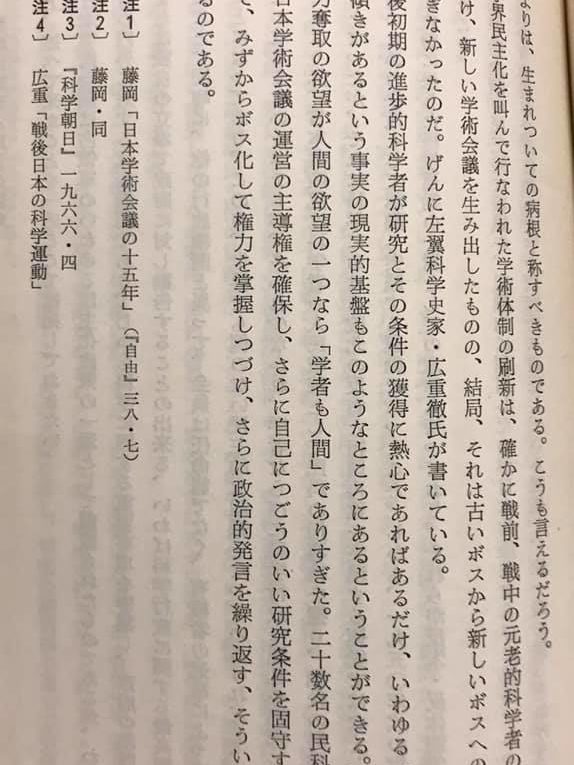学者選挙と諮問に弊害生ず
学術会議法によると、日本学術会議は選挙された二百十人の会員をもって組織され、その会員の任期は三年、ただし再選は妨げない(法七条一・二項)とある。
その、世界でも稀有の第一回学者選挙が二十三年十二月行なわれ、急進派の民科が三十名も当選者を出して注目された。元埼玉大学長の藤岡由夫氏は、学術会議の成立当時をふりかえって、次のように述べている。
「学術会議のできるまえには、学者の選挙に運動などする人はあるまいと誰もが信じていた。(中略)世間では学術会議の選挙は非難の対象となった。投票の有効無効をめぐって訴訟さわぎまであったのは、一層世間の信用を落とした。選挙に対していろいろな不正が行なわれるということ、ことに選挙について何も罰則がなくて、勝手なことをするということは、国会議員などからの非難の的となった。……そんな事もはじめは予想されなかったことで、学者は専門の学問の優劣と、会員としての適不適の判断から選ぶであろうと、考えられていたのである。しかし、いよいよやってみると、学者も人間、そんな判断は非常に難かしく、それよりも、もっと次元の低い判断で投票されてしまった。学術会議のできたころ、民主主義科学者協会という団体があった。そして選挙のたびに特定の科学者の推薦をしたが、これがなかなか有力であった。よく『学術会議は左翼の学者の集まりである』と非難されるのは、この運動をさすらしい。」〔注1〕
これが弊害の第一である。
弊害の第二は運営。学術会議は最初の総会(二十四年一月)から、その運営方針をめぐってもめた。第一回の会長、副会長選挙(法八条・互選)の模様を藤岡氏は、つづけてこう述べている。
「最初の学術会議が開かれ、会長、副会長を選ぶとき大もめにもめた。古い人たちは銓考委員会を作り、候補者をきめて投票しようと提案した。これは戦前の普通の考え方である。しかしこの考え方は、革新系の人々の猛反対にあった。『休けい等するから悪い相談をする。このまま会議を続行し、皆がもつフレッシュな気持ちの消えないうちに投票して、ただ一回の投票で比較多数を決めるのがよい』というのである。これは一部に下相談ができていたことを意味する。結局休けいをせずに、候補者も決めずに投票を行ない、ただ比較多数にはよらず、絶対多数の者がないときは同じ投票を繰り返すことにした。第一回以来学術会議の(会長・副会長)選挙はいつもこの方法で行なわれているが、三回くりかえすうちには、いつも絶対多数をうる人が出てくるのが常である。しかし、何回投票してもその得票数が大して減りも増しもしない人もいる。こういう人々にはあらかじめの話合いによる組織票があるなと察せられる。これは今でもある。」〔注2・傍点筆者〕
第三の弊害は、勝手な法規解釈である。学術会議第一回総会のころ、後に学術会議第三期、第四期にかけて会長になった茅誠司氏は、請われて文部省科学教育局長であったが、そのとき焦点となった出来事を、次のように述べている。
「当時、(文部省科学教育局長を)固辞したが受入れられず、やむなく短期間(九ヵ月)この職にあったわけである。学術会議が出発したときの、一番大きい問題は、大学管理法を作るということだった。このとき学術会議はこの問題を非常に重視して、この問題について政府は学術会議の意見をきくべきだという結論となった。当時の文部大臣は下條康麿氏、次官は井出成三氏であったが、文部省では学術会議などが差出がましいことをするのはけしからんという空気が濃厚であって、間に挟まった私は大いに苦労したものである」〔注3〕
茅氏が「大いに苦労し」なければならなかったのは、大学管理法をつくるならこちらの意見を聴け、といってきた学術会議側の気負い立った要求、つまり茅氏自身が設立に参画した学術会議側の要求と、学術会議にそのような権限は法的にない、従って政府側からは意見をきく義務はない、とする文部省見解との板挟みとなったためである。
すこし説明がいる。日本学術会議法第四条に、
「政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究員等に関する予算編成の方針
三 特に専門家学者の検討を要する重要施策
四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項」とある。
つまり、学術会議の職務、権限を定めた条文である。法律によれば当然「政府は、諮問することができる」のであって、「諮問しなければならない」というのではない。また、大学については、学術会議には法的に、勧告したり、まして答申する職務も権限もない。冷静な第三者の目からすれば、学術会議が強引に「意見を聴け」というのは越権、独善的横車であるはずである。
ここに前述、もう一つの「もしも」が出てくるのだ。学術会議内部では割合知られた裏話である。
さきの学術体制刷新委員会の答申案、この案には当初、確かに「政府は学術会議に諮問しなければならない」としてあった。しかし、この政府を義務付ける条文には行き過ぎがあるとして、反対したのは、GHQにあってS・Lと連絡しつつ学術会議創設を提唱したC・ケーリィ氏ら学術担当行政官であった。ケーリィ氏らの歯止めによって、現行「諮問することができる」条文になったわけだが、「もしも」この反対がなかったら、学術会議はとほうもない権力を持つ機関になっていたに違いない。なぜなら、そういう歯止めがあるにもかかわらず「今でも」学術会議は、同じことを繰り返しているからである。それは、こういうことなのである。
現在、学術会議はすでに第八期(四十四年一月~四十六年十二月)の半ばになるが、同会議内に会員十二名からなる「あり方特別委員会」という奇妙な名称の特別委員会がある。学術会議のあり方を検討しようという委員会だが、ここで「政府諮問」について次のように規定解釈している。
「政府が諮問できる条項として、四事項が項目として明記されている以上、これはむしろ諮問を義務づけていると読むべきであり、四事項について学術会議の答申をまたずに、政府が実施に移すことはあり得ないと考えるのが法解釈の常識である」(傍点筆者)
独断きわまりない三百代言的法解釈というべきであろう。ここに学術会議の二十年変わらぬ姿勢がある。
右、選挙、運営、法解釈について三つの事例を当事者の回顧から引用した。これは弊害などというよりは、生れついての病根と称すべきものである。こうも言えるだろう。
学界民主化を叫んで行なわれた学術体制の刷新は、確かに戦前、戦中の元老的科学者の支配をしりぞけ、新しい学術会議を生み出したものの、結局、それは古いボスから新しいボスへの権力移行にすぎなかったのだ。げんに左翼科学史家・広重徹氏が書いている。
「戦後初期の進歩的科学者が研究とその条件の獲得に熱心であればあるだけ、いわゆる”ボス化”する傾きがあるという事実の現実的基盤もこのようなところにあるということができる。」〔注4〕
権力奪取の欲望が人間の欲望の一つなら「学者も人間」でありすぎた。二十数名の民科系科学者は、日本学術会議の運営の主導権を確保し、さらに自己につごうのいい研究条件を固守するためと称して、みずからボス化して権力を掌握しつづけ、さらに政治的発言を繰り返す、そういう循環を重ねるのである。
―「学者の国会」日本学術会議の内幕 時事問題研究所編,1970年より)