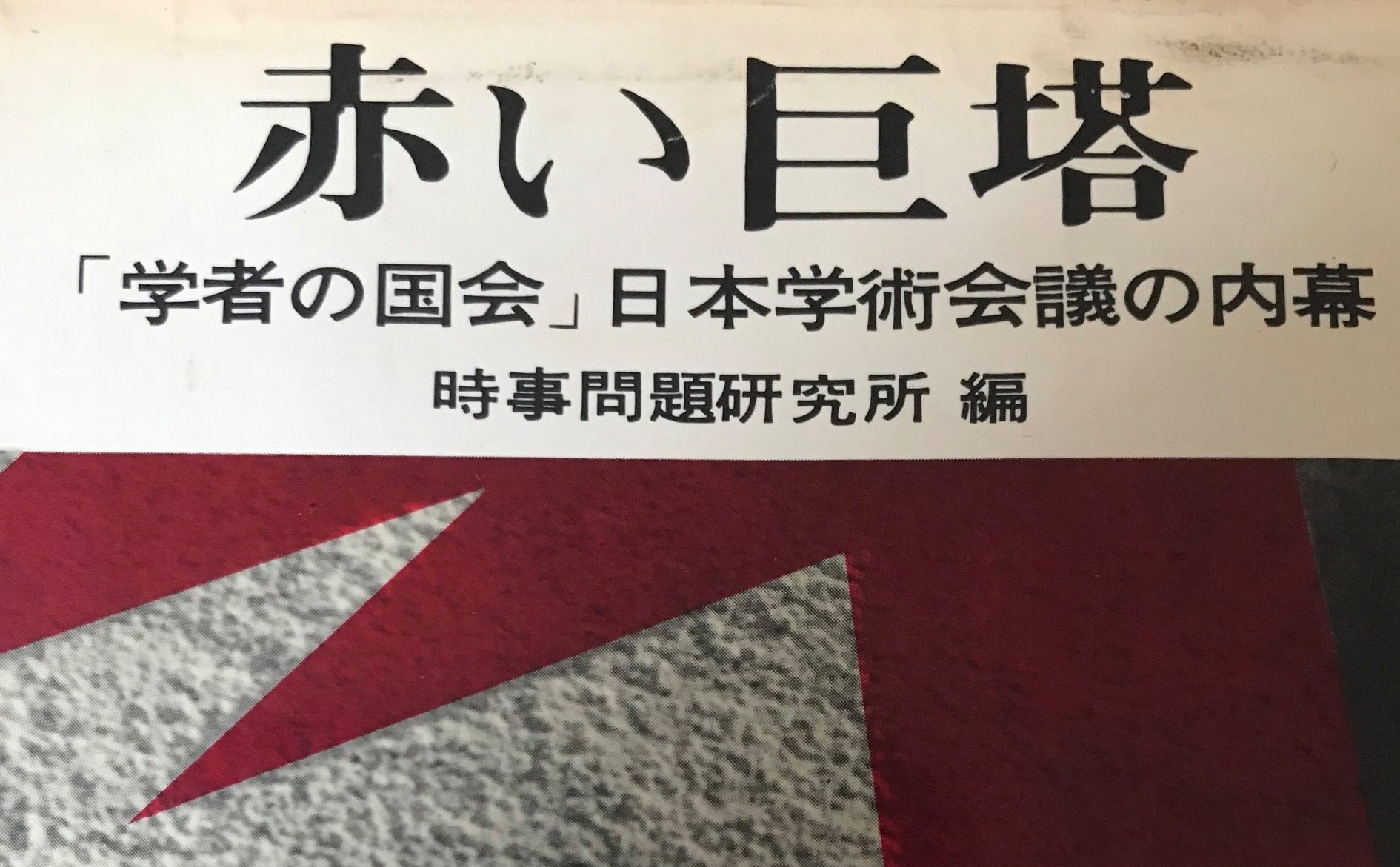謀議でつくられる「学者の総意」
前東京教育大学々長 三輪知雄
日本学術会議の実態は、学者のあいだではしだいにわかってきているが、一般世間の認識はまだまだきわめて浅い。学術会議は一種の学者集団であるが、学者というものに対する日本人の見方はひじょうに甘く、学者と聞いただけで偉そうに見え、その言うところは無条件に近く信頼される傾向が強い。したがって、このような学者の集りとしての学術会議は世間から漠然と高級なものに見られているのである。学者と呼ばれる人たちには大学の教師が多いが、大学という社会は世間を騒がせた紛争の経過からもわかるように、大学自治と称するカーテンによって閉鎖された特殊社会であり、そこを職場とする教師たちにはお坊ちゃん的な甘さがあり、独りよがりの色合いが濃く、またおしなべて反権力的である。このような環境は”進歩的”左翼の育つ絶好の場であって、学術会議はおもにこのようなところから送り出された人たちから成立っている。
戦後発足当時は良識会員が今よりもはるかに多く、その活動ぶりにも非難の声はあがらなかったが、時が経ち会員の改選交代がくりかえされるとともに左翼会員がふえ良識派は退潮の一途を辿っている。
もともと共産党の戦術は、何らかの組織体または集団があると、そこにはいりこんで橋頭堡をつくり、これを占領しようとするものである。学術会議のようなところが狙われるのは当然である。共産主義者は権力を握るため民主化という甘言で偽装し、その実少数独裁の体制をつくりあげるのであるが、学術会議でもこの線で左翼学者の活動が露骨に行われている。一部のものが予め謀議して決めたことが公の会議で「学者の総意」を僭称してまかり通るのである。一人一党の良識派の太刀打ちできるところではない。
学術会議の正常化には、何よりもまずその実態を一般に知らせ世論を喚起することである。良識学者を多数送ることによって改革するのは理想であるが、筆者はこれには悲観的である。行きつくところまで行かせてからということになるのであろうか。
(「赤い巨塔」(1970年) 時事問題研究所 編 182頁~183頁より)
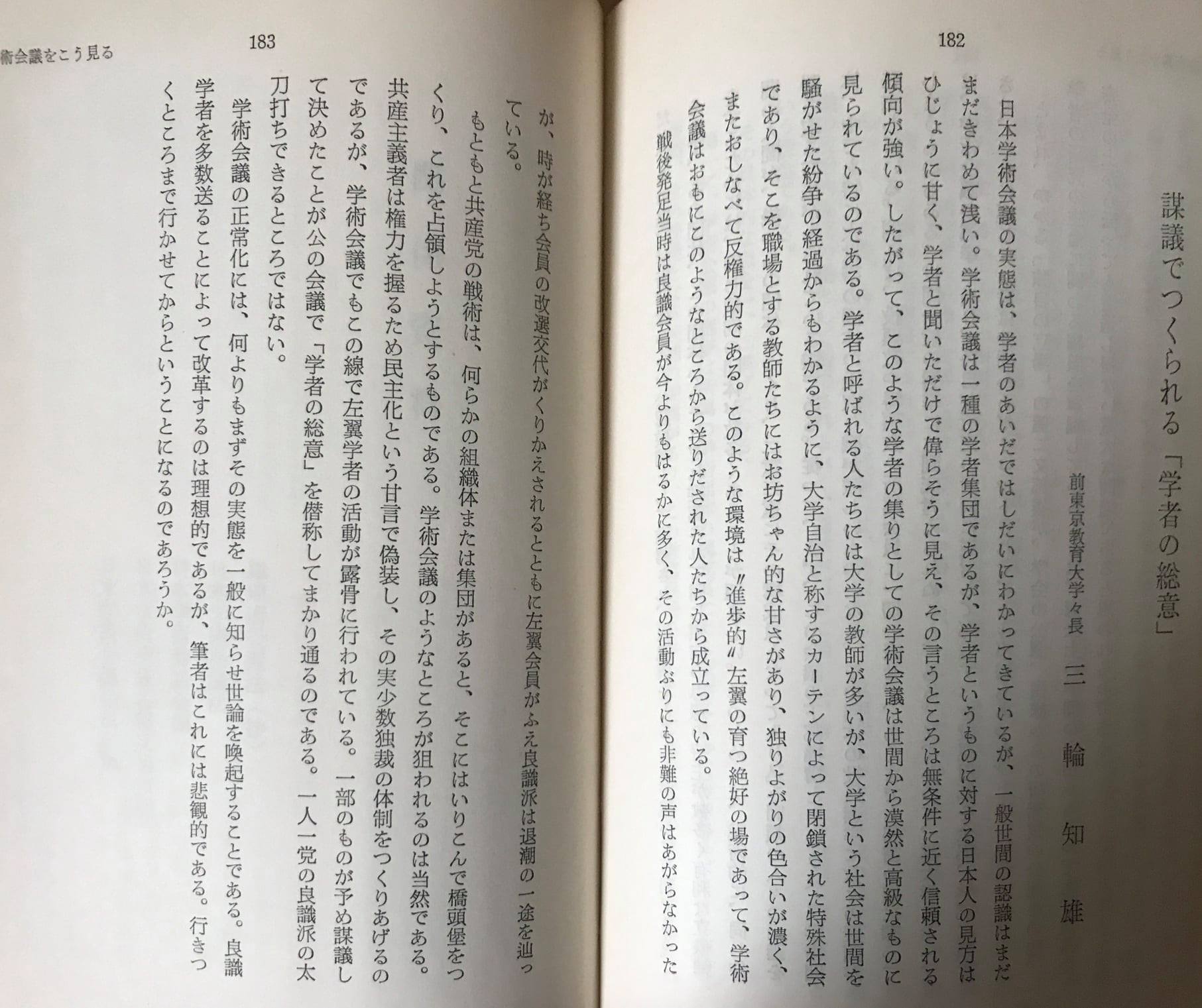
関連書籍